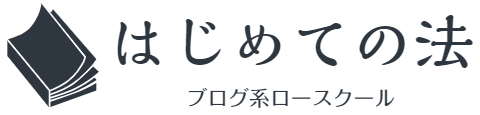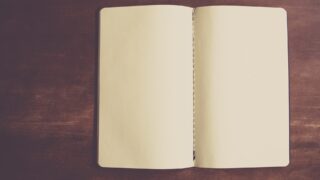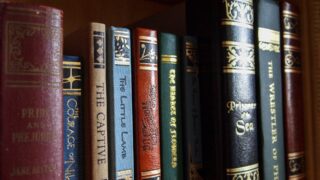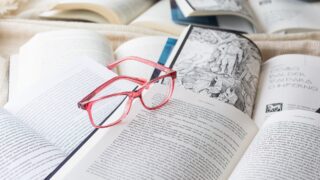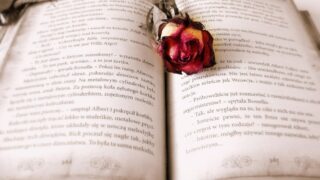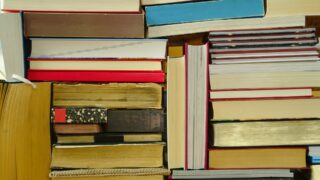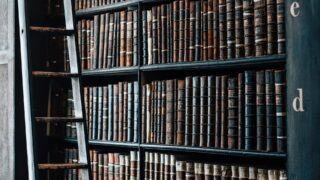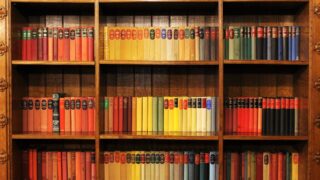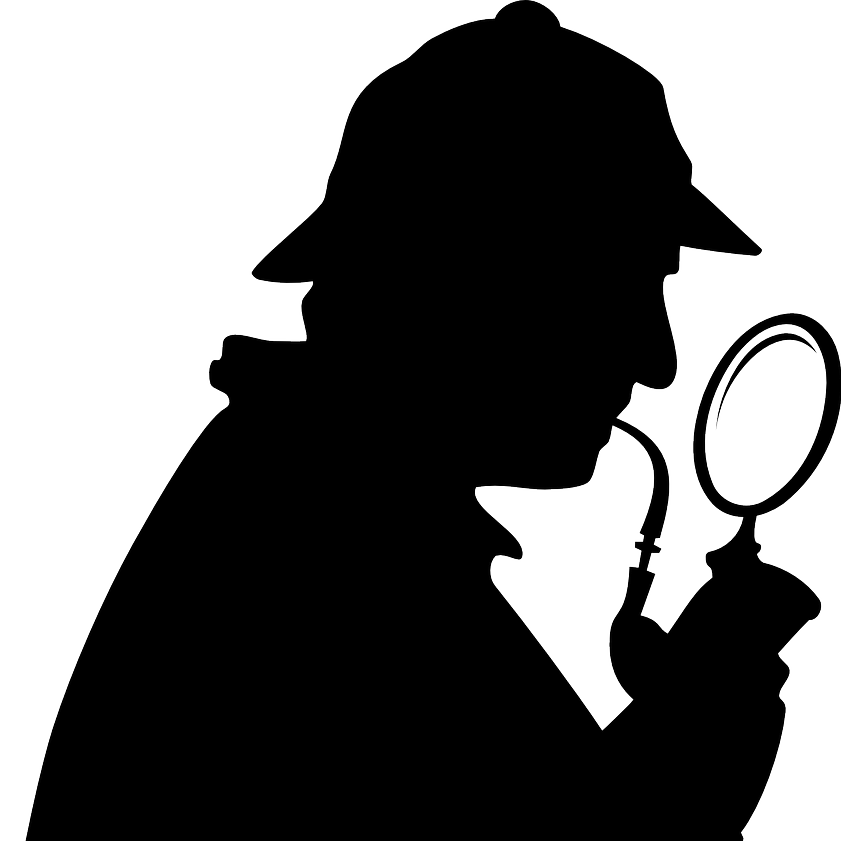
逮捕・勾留には,逮捕前置主義・事件単位原則・一罪一勾留の原則,さらに再逮捕再勾留の禁止といった多くの原理原則が登場するよね。整理できてるかい?
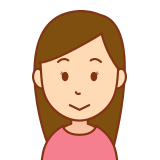
逮捕・勾留の箇所で一番悩むのがそこなんですよね。それぞれの原則の違いや適用場面がどうなっているのか,どのような関係になっているのかわかりません。
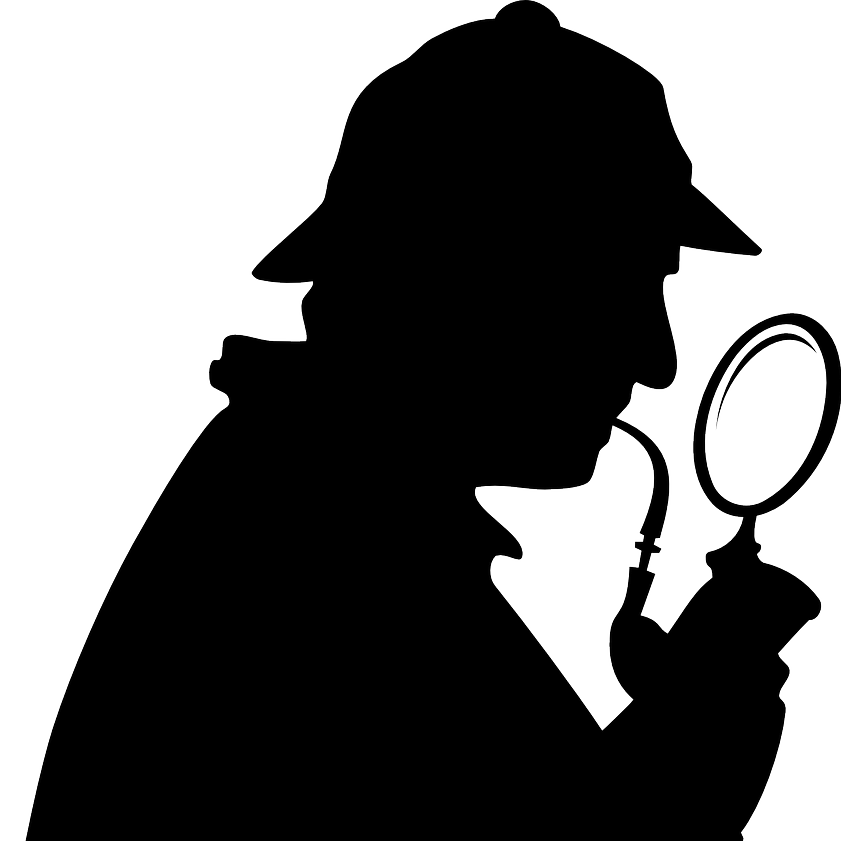
なるほど,じゃあ今回はその原則を逮捕・勾留の考え方とともに振り返ってみようか。
逮捕・勾留は刑事訴訟でよく登場する事柄ですが,それ自体が問題となることは少なく,さらにそれに関連する原理原則が多岐にわたるため,こんがらがった状態で次の分野に進んでしまうことが多いと思います。
今回はこの原理原則を整理する!という目標のもと記事を書いていこうと思います。
逮捕・勾留のポイント
逮捕・勾留について,まず要件を確認する必要があります。次に,原理原則,特に逮捕前置主義・事件単位原則・一罪一逮捕一勾留の原則を考えていこうと思います。
②逮捕前置主義について考える。
③事件単位原則について考える。
④一罪一逮捕一勾留の原則について考える。
逮捕・勾留の要件
逮捕の要件
要件を確認するには,まず条文をみるところから始まります。逮捕については刑事訴訟法199条が参考になります。
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
①逮捕の理由(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)
②逮捕の必要(罪証隠滅・逃亡のおそれ)
勾留の要件
勾留の要件に対していくつか考え方がありますが,要件を考えるにはやはり条文をみていくのが手っ取り早そうです。勾留についての条文を見てみましょう。
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。一 被告人が定まつた住居を有しないとき。二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
以上をまとめるとこのようになります。
①勾留の理由(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由+刑訴60条各号事由)
②勾留の必要(勾留により得られる公益上の利益VS被侵害利益)
逮捕前置主義の考え方
逮捕前置主義が設けらた理由
次に,第1の原則の逮捕前置主義について考えてみましょう。逮捕前置主義とは勾留のためには逮捕を経ないとダメだよ,という原則です。
ここで意識してほしいのは,刑事訴訟においては勾留がデフォルトということです。しかし,勾留してしまうと多くの時間,被疑者を拘束してしまうことになります。そこで,比較的短期間の拘束である逮捕を勾留の前に設けたのです。なので「逮捕前置」主義というわけですね。あくまで勾留がデフォルトということがこの文言からもわかります。
かっこよく逮捕前置主義の理由を説明すると,不要不当な身体拘束を避ける,という解答になると思います。
逮捕前置主義が問題になる場面
では,この逮捕前置主義が問題となるのはどのような場合でしょうか。
簡単な例としては,逮捕を経ていないのに勾留をする場合です。これは完全に逮捕前置主義違反ですよね。
しかし,例外があります。それはAという事実で逮捕し,勾留する際,Aの事実にBの事実を加えて勾留する場合です。この場合は例外的に逮捕前置主義違反とはならないとされています。
なぜ,Aの事実で逮捕して,AとBの事実で勾留することが許されるのでしょうか?これはもしこれが許されないとするとどうなるかを考えればわかります。
上記の例外的な措置が許されないとすると,Bの事実で逮捕→勾留の手続を経ないといけません。すると,こちらの方が被疑者にとっては身体拘束の期間を延ばすことになるのです。
逮捕前置主義の違反は常識的に考えればわかります。そのため,問題として出るとしたらこの例外的パターンでしょう。このパターンの際に間違えて逮捕前置主義違反としないように注意してください!
事件単位原則
事件単位原則とは何か?
事件単位原則はほとんど問題として登場しません。問題として登場出るとしたら,保釈の場面と取調べ受忍義務の場面くらいでしょう。そのため,理論だけを押さえていれば大丈夫だと思います。
事件単位原則は,人単位ではなく事件単位で身体拘束を考えるというものです。
Xという人がいて,Aという事実で逮捕されたとします。次にBという犯罪事実が出てきた場合,人単位説だとすでにAという事実で逮捕=身体拘束されているのでBという事実では逮捕できないことになります。
しかし,事件単位説であれば,事件ごとで身体拘束を考えればいいので,仮にXがAという事実で逮捕されていたとしても,Bという事実ではまだ逮捕されていないので,合わせてBという事実で逮捕できるということになります。
事件単位の原則が問題となる場面
例外的な場面として保釈の場面があります。保釈とは起訴後の被告人を釈放することです。この際,事件単位の原則によれば,その逮捕勾留事実,起訴事実しか考慮できないと思われますが,保釈の場合は,他の事件についての事情を一資料として考慮できるとされています。事件単位の原則が緩和されているというわけです。
このように事件単位の原則は厳格に取り扱われていないこともあり,問題となることは少ないと思います。
一罪一逮捕一勾留の原則
一罪一逮捕一勾留の原則の考え方
最も逮捕勾留で問題となるのが,この一罪一逮捕一勾留の原則です。これに関連して再逮捕再勾留の禁止が出てきます。
簡単に言うと,一罪一逮捕一勾留の原則とは一つの事件について一つの逮捕,一つの勾留しかできないという原則です。文字通りですね。
この一罪というのは実体法上一罪を指します。つまり,牽連犯や観念的競合,法条適合や包括一罪の場合ということです。
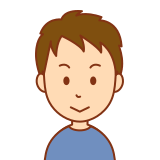
よく基本書では,実体法上一罪のことというけれど,実際どのような場合が実体法上一罪かわからなかったんですよね。
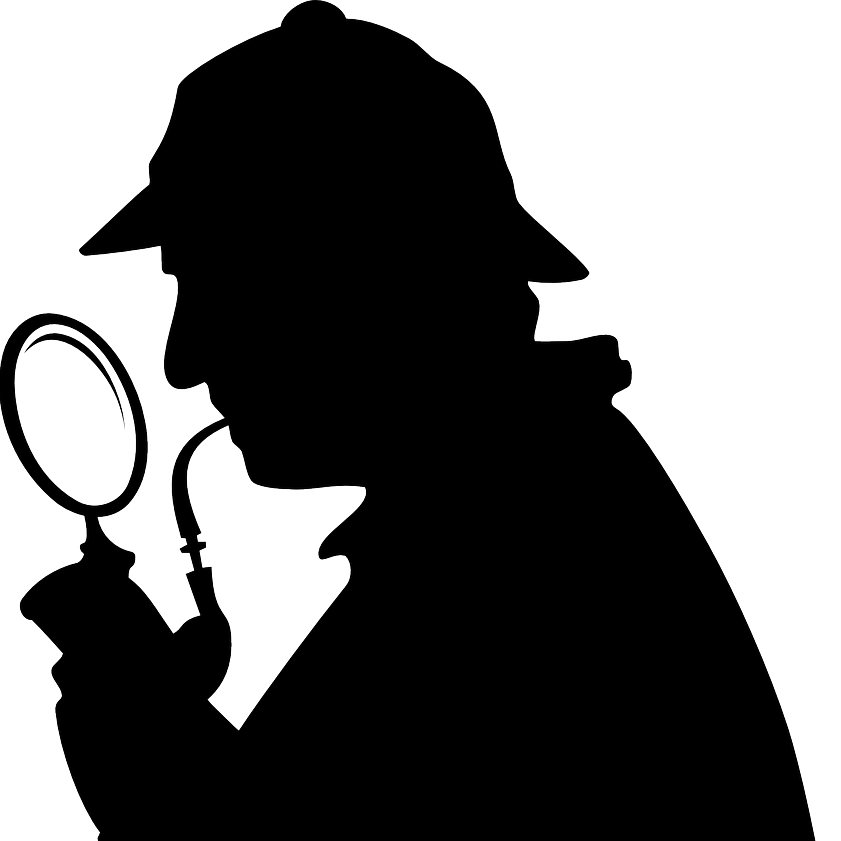
刑法でいうところの併合罪以外の類型だと考えておけば大丈夫だろう。つまり,住居侵入罪の事実で逮捕した場合は,その後の強盗罪で逮捕することは基本的にできないというわけさ。牽連犯で実体法上一罪だからね。
さらに問題になるのが再逮捕再勾留の禁止
この一罪一逮捕一勾留の原則から派生して出てくるのが再逮捕再勾留の禁止です。
同じ犯罪事実で逮捕や勾留をすることは,一罪一逮捕一勾留の原則に反するので原則禁止であることを言っています。あらかじめ分かっている犯罪であればその際に逮捕すべきであったというわけですね。
しかし,これは原則なので例外がいくつかあります。2パターン見ていきましょう。
捜査可能性から例外的に許される場合
それは逮捕や勾留の釈放後に新たに実体法上一罪となる罪を犯した場合です。この場合はたしかに,再逮捕再勾留の禁止に該当しそうですが,捜査機関としては当初の逮捕時に問題となっている事実は知らなかったわけですから当初の犯罪捜査時に新たにわかった犯罪事実で逮捕することはできませんでした。すなわち,捜査機関はこの問題をどうすることもできなかったわけです。
この場合は再逮捕再勾留の禁止の例外的な場合となり,オッケーというわけです。
純粋に条文上許される場合
再逮捕再勾留の禁止とうたっていますが,絶対的禁止というわけではなく,条文でも再逮捕再勾留が許される場合が規定されているとされています。
特に再逮捕については刑事訴訟法199条3項が根拠になります。
第百九十九条3 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
先ほどの逮捕前置主義の議論を踏まえれば,あくまで勾留がデフォルトですので,再逮捕が許されるのであれば再勾留はもちろん許されることになります。ここで問題になるのはどのような場合に許されるのかです!
先の逮捕後の事情の変更,事案の重大性,事情変更による再逮捕の必要度,先行逮捕・勾留の身柄拘束期間とその間の捜査状況などを考慮して,被逮捕者の利益と対比してもやむをえないとき
まとめ
以上,逮捕勾留についての原理原則である,逮捕前置主義,事件単位原則,一罪一逮捕一勾留の原則,それに付随する再逮捕再勾留の禁止を見てきました。
最後にこれらをまとめて整理してみます。
②事件単位原則が問題となるのは,保釈,取調べ受忍義務くらいのなのでそれほど問題視しなくてよい。
③一罪一逮捕一勾留での主な問題は再逮捕再勾留の禁止であり,例外的に実体法上一罪であっても釈放後の犯罪や「必要」が高度でやむを得ない場合は再逮捕再勾留も許される。
読んでくださってありがとうございました。ではまた~。
参考文献
刑事訴訟法の参考文献として「事例演習刑事訴訟法」をお勧めします。はじめての方にとっては解説が大変難しい問題集ですが,非常に勉強になるものです。また,冒頭にあります答案作成の方法について書かれた部分については,すべての法律について共通するものなのでぜひ読んでほしいです。自分も勉強したての頃にこれを読んでいれば……と公開しております。
最初は学説の部分はすっとばして問題の解答解説の部分だけを読めばわかりやすいと思います。冒頭の答案の書き方の部分だけでも読む価値はあるのでぜひ参考にしてみてください。