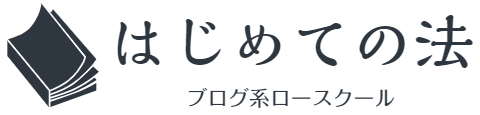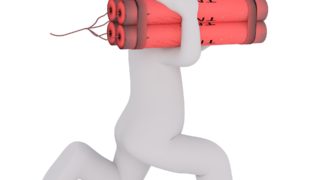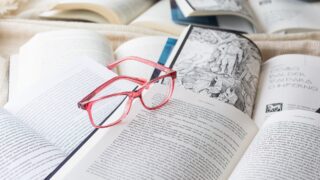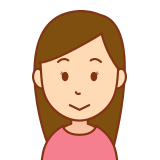
抱き合わせ販売について教えてください!
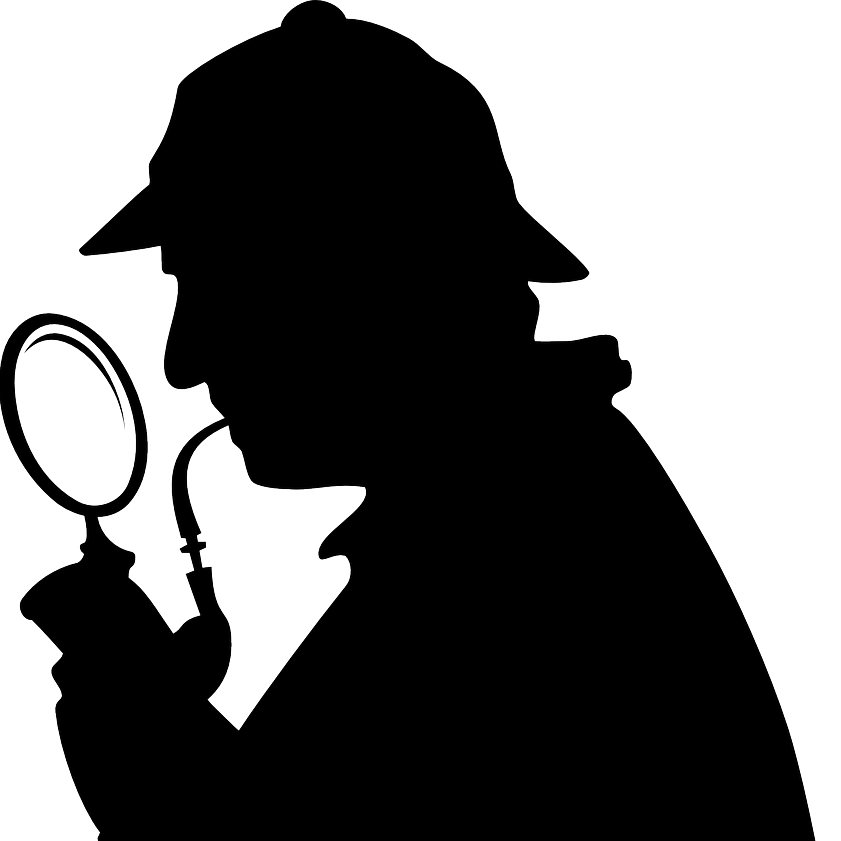
お!抱き合わせ販売はなかなか判例・事案が面白いから勉強が楽しいと思うぞ!
しかし今回は要件の確認だけだから深入りはしないけどね。
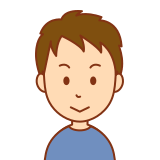
たしか抱き合わせ販売といえば「マイクロソフト」ですよね。WordとかExcelとか今でもなじみのあるを抱き合わせ販売してやらかしてますからね。
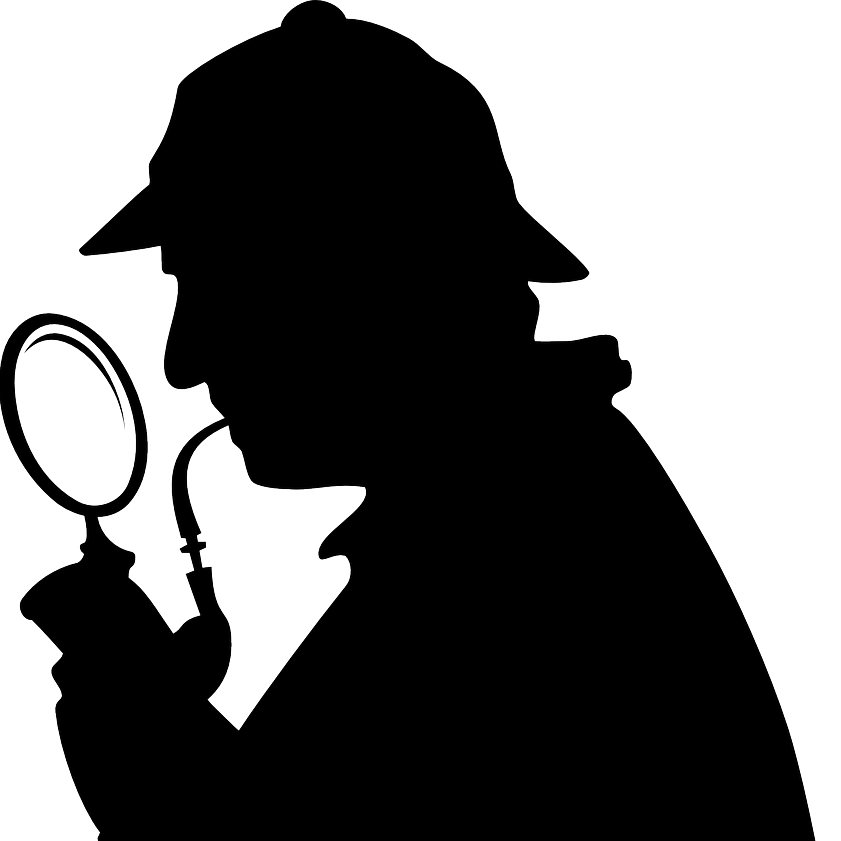
そうだね!ぜひこの記事で抱き合わせ販売について要件を確認した後は、百選等でマイクロソフト事件についてみてほしいね!
不公正な取引方法の1つ、抱き合わせ販売についてみていきましょう!
抱き合わせ販売は要件自体特有のものが多いですが、不当廉売ほど覚えることは多くありません。そのため、要件自体はすんなり理解できると思います。
抱き合わせ販売はマイクロソフト事件が有名です。一太郎対Wordの逆転のきっかけにもなったマイクロソフトがとった戦略が抱き合わせ販売でした。
このように学習していて面白い分野でもあります。抱き合わせ販売の何がいけないのか。要件の解釈はどうなっていくのか、しっかり確認していきましょう!
抱き合わせ販売のポイント
抱き合わせ販売はひたすら要件を確認することに尽きます。行為自体もわかりやすいので、他の不公正な取引方法と比べてなぜ違法になるのか、わかりにくいということはないでしょう。
とはいえ、抱き合わせ販売とは何かをざっと解説したあと、要件の「他の商品」、「購入させる」、公正競争阻害性についてしっかり押さえていこうと思います。
①抱き合わせ販売とは何か、理解する。
②要件「他の商品」について理解する。
③要件「購入させる」について理解する。
④公正競争阻害性について理解する。
それではみていきましょう。
抱き合わせ販売とは何か?
要らない商品と一緒に買わせる
抱き合わせ販売とは、必要のない商品まで合わせて買わせるという手段です。
たとえば、商品がめっちゃ余っている、人気のない商品を、人気のある商品とともに売るという行為が抱き合わせ販売になります。
すると、消費者はわざわざ人気のある商品がほしいがために要らない物まで購入することになりますよね。これによる公正競争阻害性(競争手段の不公正さ・自由競争減殺)を規制しているというわけです。
条文は一般指定10項
これまでの不公正な取引方法とは異なり、抱き合わせ販売は適用条文で間違うことはありません。1つだからです。しかも事案もわかりやすいので、抱き合わせ販売という論点に気づくこともすぐにできるでしょう。
それでは一般指定10項をみてみます。
(抱き合わせ販売等)
10 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。
要件を抜き出すと、③「不当に」①「他の商品」②「購入させ」になります。
※便宜上、条文の順番から変えています。
それではそれぞれの要件についてみてきましょう。
要件①:「他の商品」
「他の商品」は独自性を有し、独立して取引の対象とされているかどうかという観点から判断されます。
逆に言えば、抱き合わせに使われる「他の商品」はそれ自体で商品としての価値を持っていなければならないというわけです。
たとえばシャーペンの上の方の消しゴムとシャーペン自体について考えてみましょう。

シャーペンの消しゴムとシャーペンは最初は一緒に売られていますよね?これは抱き合わせ販売でしょうか?
ここでシャーペンの消しゴムに独自性があるかどうかを判断します。シャーペンの消しゴムはそれ単独で販売されていることはほとんどないと思います。つまりシャーペン消しゴムに独自性はないというわけです。
よって、シャーペンの消しゴムは「他の商品」に該当せず、シャーペンとともに販売されていても抱き合わせ販売には該当しません。
また、独自性がある物であっても、複数の商品を組み合わせることにより、内容・機能において新たな価値が加えられ、抱き合わせ前のそれぞれの商品と比べて実質的な変更がもたらされる場合や、組み合わされた商品が通常1つの単位として販売・使用されている場合なども、単一の商品であり、「他の商品」という要件には該当しないことになります。
シャーペンの消しゴムはこの考え方にも該当しますね。
要は「他の商品」の要件は
①独自性(独立した取引対象)があるかどうか
→②独自性があったとしても
㋐組み合わせによって新たな価値が加えられる
㋑通常1つの単位として販売・使用される
と充足するというわけです。
要件②:「購入させ」る
「購入させる」という言葉を聞いて、強制的に買わせるというイメージを持ちがちですが、抱き合わせ販売の「購入させる」にそこまでの強さは要求されていません。
客観的にみて、従たる商品を購入しなければ主たる商品を供給しないという関係が成立し、少なからぬ顧客が従たる商品の購入を余儀なくされているかどうか(藤田屋事件参照)
によって判断されるとされています。
たとえば、人気商品と人気のない商品との抱き合わせは、人気商品の欲しさ、需要の高さ、希少性から、人気のない要らない商品(従たる商品)を買わざるを得ない場合、「購入させる」に該当するわけです。
「要らないなら買わなければいいよ!人気商品単独では売ってあげないけどね!」
「それならセットで買います……(泣)」
のような場面は、実際に強要しているわけではないですが、「強制させ」ているというわけです。
要件③:「不当に」(公正競争阻害性)
最後に「不当に」の要件です。これは不公正な取引方法ではおなじみの文言で、「公正競争阻害性」を意味します。
>>>不公正な取引方法共通の「不当に」「正当な理由がない」の意味【経済法その5】
さて、抱き合わせ販売の公正競争阻害性は毎度おなじみ「自由競争減殺」以外にも「競争手段の不公正さ」とタイプがあることは忘れないようにしましょう。
競争手段の不公正さは、従たる商品の購入を強いられ、顧客による商品・役務の選択の自由を妨げるおそれのある競争手段であることそれ自体が問題となるため、競争への影響は見ないことになります。
しかし実際は競争手段の不公正さという観点は使われず、現在の実務では「自由競争減殺」の観点で公正競争阻害性を見るのが一般的です。
自由競争減殺の場合は、主たる商品の市場における有力な事業者による抱き合わせ行為を通じて、従たる商品の市場において市場閉鎖効果が生じるかどうかをみます。
つまり、市場を画定し、その中での新規参入者や既存の競争者の排除又は取引機会減少の状態を見るというわけです。
シェアや行為内容、他の事業者状況
などが大事というのは、自由競争減殺や競争の実質的制限の考え方と同様です。
まとめ(論証)
抱き合わせ販売をみてきました。抱き合わせ販売は要件も少なく、適用条文も1つしかないため、他の不公正な取引方法と比べて「わかりやすい」でしょう。
論証自体も「覚える」ものではありませんが、「他の商品」の要件を満たすかどうかがキーポイントになっているので、しっかりと考え方は押さえたい所です。
「他の商品」
①独自性(独立した取引対象)があるかどうか
→②独自性があったとしても
㋐組み合わせによって新たな価値が加えられる
㋑通常1つの単位として販売・使用される
読んでくださってありがとうございました。ではまた~。
参考文献
経済法を本格的に学習する人の中で入門的に使ってほしい参考書を上げてみます。というか論証の暗記として使えるものを用意してみました。
とりあえず経済法のスタートは「要件の暗記」です。そのため、要件自体のガイドラインや判例通説をもとに逐条的に解説してある『条文から学ぶ独占禁止法(第2版)』をおすすめします。